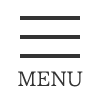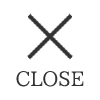第7回異と和~違いが調和を紡ぐ時代へ~議事録2025.07.07

令和7年7月6日
仙台奥羽ロータリークラブ7月臨時例会
MRオープンカフェ第一部
現代社会とメンタルヘルス
発表者
● ファシリテーター: キッセイ薬品工業株式会社 蒔田愛斉氏
1.日本におけるメンタルヘルスの現状と課題、及び社会的取り組み
● メンタルヘルス不調の身近さと影響
メンタルヘルス不調は身近な問題であり、うつ病や統合失調症、依存症、発達障害など様々な精神疾患につながる可能性がある。著名人にも多くの事例があり、社会全体で考える必要がある。
● 本日のアジェンダ
メンタルヘルスの現状、日本の現状、現状を踏まえた取り組み、仏教の教えとの関連、ディスカッションと発表の流れで進行することを説明。
● 日本のメンタルヘルスを取り巻く社会環境
ライフステージごとのストレス(学生生活、仕事、結婚、子育て、介護)、働く環境、ハラスメント、デジタル化による誹謗中傷や炎上、悲しいニュースの影響、人間関係の希薄化、孤独感、新型コロナウイルスによる不安などが挙げられる。
● 精神疾患患者数の推移
厚生労働省のデータによると、精神疾患を有する総患者数は約603万人。平成14年から令和5年まで増加傾向。平成29年から令和2年に統計方法の変更があったが、全体的に増加している。
● 外来患者数と疾病分類別内訳
外来患者数は約576.4万人。最も多いのは気分障害、次いで神経症性障害・ストレス関連障害・身体表現性障害、三番目が統合失調症・妄想性障害。
● 精神病床数の国際比較
日本の精神病床数はカナダやフランスなど他国と比べて圧倒的に多い。医療が充実している一方、偏見や差別、地域ケアの困難さから入院せざるを得ない現状が課題。
● 企業におけるメンタルヘルス不調の影響
2021年の調査で、メンタルヘルス不調により連続1か月以上休業または退職した労働者がいた事業所の割合は10.1%(前年より0.9%増)。2020年11月1日~2021年10月31日の調査では、休業8.8%、退職4.1%でいずれも増加傾向。1000人以上の事業所では休業92.5%、退職68.6%。
● 若年無業者の現状
総務省労働力調査によると、15~34歳の若年無業者は令和4年で平均57万人、人口比2.3%。就業構造基本調査では、就職活動をしていない理由の最多は病気・怪我であり、精神疾患も含まれると考えられる。
● 世界メンタルヘルスデーの紹介
世界メンタルヘルスデーは10月10日。世界精神保健連盟が1992年に制定し、WHOも協賛。世界的な国際記念日としてメンタルヘルス問題への意識向上、偏見解消、知識普及を目的としている。
2.メンタルヘルスの現状と仏教的アプローチによる心の健康維持
• 2024年世界メンタルヘルスデイのテーマと2025年の予定
2024年の世界メンタルヘルスデイのテーマは「今こそ職場でメンタルヘルスを優先しよう」であり、2025年のテーマは未発表だが、2025年10月10日に開催予定であることが確認された。
• 日本における学校生活でのメンタルヘルスへの取り組み
10代・20代は精神疾患にかかりやすい時期であり、2018年3月に高校の学習指導要領が改定され、保健体育に精神疾患の予防と回復が盛り込まれた。体の健康と同様に心身の不調への気づきや早期発見、社会的対策の重要性が学ばれている。
• 企業におけるメンタルヘルス対策の現状
メンタルヘルス対策を実施している事業所は59.2%。主な取り組みはストレスチェック(65.2%)、職場環境の評価・改善、相談体制の整備、メンタルヘルス不調者への配慮など。具体的な企業事例も紹介された。
• 企業の具体的なメンタルヘルス施策事例
株式会社友人エンジニアリングは月1回の外部EAP・産業医面談を実施。株式会社ニチレイは東北1名、関西1名、九州2名のエリア保健師を配置し、50人以上の事業所で産業医を選任。株式会社八天堂は社内アンケートやストレスチェック、臨床心理士のいる病院との連携を行っている。
• 仏教の教えとメンタルヘルス
仏教は約2500年前に釈迦仏陀によって始まり、苦しみからの解放を目的とする。現代の心の問題解決策として注目されている。
• 仏教的メンタルケアの10項目
1.マインドフルネスで現在に集中 2.無常観の理解 3.慈悲の実践 4.煩悩の理解とコントロール 5.禅の知恵 6.過去への執着を手放す 7.正しい言葉と行動 8.精進と自己修養 9 中道の実践 10.知足の心で今ある幸せに気づく。各項目の具体的な実践方法も紹介。
3.精神的な不調や気分の落ち込みへの対処と今後の対応策
• 精神的な不調や気分の落ち込みへの対処法
参加者が気分が落ち込んだ時やストレスを感じた時の対処法について、自身や部下、家族の経験を交えて意見交換を行った。具体的な方法や考え方、日常のルーティン、運動、休暇の取り方などが共有された。
• 今後の負荷増大時の対応や企業として必要なこと
今後さらに大きな負荷がかかった場合や、個人・企業としてどのような対応が必要かについて意見交換を行うことが提案された。
4.ストレス対処法の共有と仏教的視点による心の持ち方
• ストレス解消法・対処法の共有
参加者が自身のストレス解消法や対処法(食事、音楽、睡眠、自然とのふれあい、料理、ポジティブ思考など)を具体的に共有した。
• 仏教の教えとストレスの関係
仏教の十項目や中道の考え方がストレス軽減や日々の心の持ち方に役立つことが議論された。
• ストレスの定義と社会構造への疑問
ストレスという言葉や概念自体が社会構造に影響されていること、善悪や健康・病気の二元論に陥る危険性について問題提起があった。